
インターネットの利便性が高まるにつれて、その裏側で深刻化しているのが、個人のプライバシーを暴き、晒し上げる「特定行為」の激化です。日常的なSNSのちょっとした投稿、オンラインゲームでの口論、あるいは不確かな「炎上」情報がきっかけとなり、匿名のはずの個人が、瞬く間に本名、住所、勤務先、家族構成といったセンシティブな個人情報をネット上に暴露されてしまう。このような行為は、単なる迷惑行為にとどまらず、被害者に対して深刻な精神的苦痛、名誉毀損、経済的な損害、さらにはストーカー行為などの現実的な危険をもたらす重大な誹謗中傷であり、現代社会における最大のネットトラブルの一つとなっています。
かつて特定行為といえば、一部のアンダーグラウンドな掲示板でのみ行われていましたが、現在ではその手口は巧妙化し、X(旧Twitter)、Instagram、匿名掲示板、暴露系まとめサイトなど、人目につきやすい多様なプラットフォームで拡散されるようになりました。拡散スピードは驚異的で、一度情報が公開されると、その後の「デジタルタトゥー」として半永久的に残り続け、就職・転職活動や私生活に影を落とします。こうした状況下で、一般社団法人ネット削除協会には、「自分の情報が特定された」「過去の投稿から住所を割り出された」「家族にまで嫌がらせが及んでいる」といった、特定行為による被害に関するご相談が急増しています。

本記事は、この特定行為という深刻なネットトラブルに対し、被害者側がどのように迅速かつ効果的に情報削除を進めるべきか、また、特定行為を「行ってしまった」加害者側が知っておくべき重大な法的リスクと、被害を拡大させないための対処法を包括的に解説します。
特に、最も重要となる「どうすれば削除できるのか」という具体的なノウハウに焦点を当て、情報の削除請求手続きや、プラットフォームへの対応、法的措置について具体的なフローチャート形式で詳細に記述します。特定行為から自身と家族を守り、デジタル時代の安全と平穏を取り戻すための実務的な知識を、ここで手に入れてください。
特定行為とは何か?法的定義と被害の実態
「特定行為」の定義とネットにおける変遷
特定行為とは、インターネット上に公開されている断片的な情報(写真に写り込んだ風景、SNSの投稿内容、ハンドルネーム、過去の発言など)を繋ぎ合わせ、その人物の現実世界での身元(本名、住所、勤務先、学校、顔写真など)を割り出し、それを不特定多数に向けて公開・拡散する行為を指します。
かつては、特定の巨大匿名掲示板などで、個人的な怨恨や興味本位から行われていましたが、近年では、ニュースになった事件の加害者や被害者、あるいはちょっとしたネット炎上を起こした一般人に対して、「正義の鉄槌を下す」という名目で行われるケースが増加しています。この「正義中毒」的な行動の裏側には、単なる好奇心だけでなく、晒し上げによる集団的な攻撃欲求が潜んでいることが多く、被害が極めて広範囲かつ深刻になる傾向があります。
特に、特定された情報に「〇〇社の社員だ」「過去にこんな犯罪行為をした」といった虚偽や不確かな情報が付け加えられて拡散されると、被害は単なるプライバシー侵害を超えて、名誉毀損や業務妨害のレベルにまでエスカレートします。この悪質な行為は、個人の社会的評価を著しく低下させ、生活基盤を破壊する可能性を秘めています。
特定行為が侵害する重大な権利:プライバシー権と名誉権
特定行為によって他人の個人情報がネット上に暴露された場合、主に以下の二つの重要な法的権利が侵害されます。削除を要求する際の法的な根拠として、これらの権利侵害を明確に主張することが不可欠です。
- プライバシー権の侵害: プライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されない権利」です。特定行為によって、一般には知られたくない個人の情報(本名、住所、電話番号、勤務先、交友関係など)が暴露された場合、これは明らかにプライバシー権を侵害しています。裁判所がプライバシー侵害を認めるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 私生活上の事実であること: 公的な事柄ではなく、個人の私的な情報であること。
- 一般人の感受性を基準にして、公開を望まない情報であること: 誰でも知られたくないと感じるであろう情報であること。
- 一般人に未だ知られていない事実であること: すでに公然の事実となっていないこと。 住所や本名、顔写真などは、これらの要件を満たしやすく、削除請求の強力な根拠となります。
- 名誉権・名誉感情の侵害: 特定された情報に付随して、「この人物は〇〇という犯罪者だ」「会社の金を横領している」といった虚偽の事実や、「馬鹿」「クズ」といった侮辱的な評価が付け加えられた場合、これは名誉毀損や侮辱にあたります。
- 名誉毀損: 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為です(真実であるか否かは問わない)。特定された情報に虚偽の不祥事や犯罪歴を紐づけて晒し上げるケースがこれに該当します。
- 侮辱: 事実を摘示せずに、公然と人を侮辱する行為です。特定された人物に対して、根拠のない悪口や罵倒を浴びせる行為がこれに該当します。
これらの法的根拠を整理し、証拠(特定投稿のURL、スクリーンショットなど)を揃えることが、削除請求の第一歩となります。
刑事罰の対象となる「特定行為」関連法規
特定行為は、民事上の損害賠償請求の対象となるだけでなく、刑法や特別法に基づく刑事罰の対象にもなり得ます。加害者側は、安易な行為が以下の重い罰則につながるリスクを認識する必要があります。
- 刑法上の名誉毀損罪・侮辱罪:
- 名誉毀損罪(刑法230条):3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金。
- 侮辱罪(刑法231条):1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(※2022年改正により厳罰化)。
- 脅迫罪・強要罪: 特定された情報をネタに、被害者を脅したり、特定の行為(土下座、謝罪文の公開など)を強要したりした場合、刑法上の脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)や強要罪(3年以下の懲役)が成立する可能性があります。
- ストーカー規制法違反: 特定行為の結果、被害者の住所や勤務先に押しかけたり、連続してメールやSNSのメッセージを送ったりする行為が、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)に抵触する場合があります。特定情報をもとにした嫌がらせ行為が繰り返されると、警察が介入する重大な事態に発展します。
- 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法): 特定行為の一環として、個人の私的な性的画像(リベンジポルノ)が拡散された場合、この法律により刑事罰が科されます。この法律は、被害者の同意なく、私的な性的画像を公衆に提供する行為を厳しく罰するものです。
このように、特定行為は単なるネット上のいたずらではなく、加害者を懲役刑に処す可能性のある重大な犯罪行為であることを、すべてのネット利用者は理解しておくべきです。
被害者向け:特定情報削除のための緊急対応フロー

特定行為によって個人情報がネット上に暴露された場合、被害者が抱く不安や精神的苦痛は計り知れません。重要なのは、パニックにならず、迅速かつ体系的に対応することです。
情報の拡散スピードを考慮すると、初動の遅れが被害拡大に直結します。ここでは、特定された情報をネット上から削除し、被害を最小限に抑えるための具体的な緊急対応フローを解説します。
迅速な証拠保全と被害届の提出
特定行為による被害を受けたとき、まず行うべきは「未来の法的措置に備えること」です。そのためには、情報が削除される前に、「誰が」「どこに」「どのような情報」を公開したのかを、動かぬ証拠として保全する必要があります。
1. 公開された情報の「日時・場所・内容」の記録
最も重要な証拠は、特定情報が公開されている画面そのものです。以下の項目を記録・保全してください。
- URL(ウェブアドレス)の正確な記録: 投稿ページのアドレスバーに表示されている完全なURLを正確に記録します。これは削除依頼や法的措置の際に、情報の発信場所を特定するために不可欠です。
- スクリーンショットの撮影(広範囲かつ詳細に):
- 単に問題の書き込みだけでなく、投稿日時、ユーザー名(アカウント名)、サイト名(ロゴ)、ブラウザのURL表示部分が一緒に写るように広範囲でスクリーンショットを撮影してください。投稿日時がないと、いつ公開された情報か証明できず、証拠能力が低下する可能性があります。
- 可能であれば、パソコンで撮影し、画面全体をPDF形式や印刷物として残すことも検討してください。スマートフォンでの撮影の場合は、情報が途切れないように注意が必要です。
- 動画録画による記録(掲示板・SNSの場合): 特定情報が投稿されたウェブページを、実際にスクロールして閲覧している様子を動画として記録することも有効です。これにより、情報がウェブサイトの一部であり、改ざんされたものではないことを証明しやすくなります。
2. プロバイダ情報の特定に向けた準備
特定行為を行った加害者を特定し、損害賠償請求などの法的措置を検討する場合、投稿時のIPアドレス情報を取得する必要があります。
- 発信者情報開示請求の準備: IPアドレスは、情報の公開場所であるコンテンツプロバイダ(掲示板やSNSの運営元)に一定期間(多くの場合は数か月)しか保存されていません。このため、情報の削除だけでなく、加害者特定を望む場合は、証拠保全後すぐに発信者情報開示請求の手続きに着手する必要があります。削除依頼と並行して、または削除後に情報が消えてしまう前に、この手続きを進めることが重要です。
3. 警察への相談・被害届の提出
特定行為の内容が、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、強要罪、あるいはストーカー規制法違反などに該当する可能性が高い場合は、速やかに警察に相談し、被害届の提出を検討してください。
- 刑事事件としての対応: 警察が動くことにより、プロバイダに対して捜査目的で情報提供を求める可能性が生まれます。特に、生命の危険や切迫した被害がある場合は、警察の緊急対応が最優先されます。
- 相談の窓口: 各都道府県警察に設置されているサイバー犯罪相談窓口や、生活安全課などが主な相談先となります。証拠保全した資料を全て持参し、特定行為の悪質性、被害の重大性を具体的に説明することが重要です。
プラットフォームへの削除依頼と法的根拠の示し方
自力で情報を削除しようとする場合、最も最初に取り組むべきは、情報が掲載されているウェブサイトやサービスの運営元(コンテンツプロバイダ)に対する削除依頼です。
1. サイトの「利用規約」を根拠にした削除依頼
多くのプラットフォーム(SNS、匿名掲示板、ブログサービスなど)は、特定行為やプライバシー侵害、誹謗中傷を禁止する「利用規約」や「コミュニティガイドライン」を定めています。これらの内部ルールを根拠に削除を求めるのが、最も迅速な対応策となる場合があります。
- 規約違反の特定: 問題の投稿内容が、運営元の定める「プライバシー侵害」「個人情報の公開」「嫌がらせ」「ハラスメント」などのどの規定に違反しているかを具体的に特定します。
- 専用フォームの活用: 大手プラットフォーム(Google、X、Metaなど)には、プライバシー侵害や誹謗中傷専用の報告フォームが用意されています。これらを活用し、URLと具体的な規約違反箇所、なぜ削除すべきかを簡潔に記入して送信します。
- 法的根拠を添える: 削除フォームに「法的根拠」を記入する欄がある場合、該当する投稿が「民法上のプライバシー権侵害」または「名誉毀損」に該当することを明記し、上記で保全した証拠を提出することで、プラットフォーム側も迅速に「違法性の有無」を判断しやすくなります。
2. プロバイダ責任制限法に基づく「送信防止措置請求」
プラットフォーム運営元が自主的な削除に応じない場合や、匿名掲示板など削除依頼の窓口が不明確なサイトの場合、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づく正式な手続きを踏むことになります。
- 送信防止措置請求とは: これは、情報公開によって権利を侵害された被害者が、サイト運営元(コンテンツプロバイダ)に対し、情報の送信を停止する措置(=削除)を請求するものです。この請求を行うことで、サイト運営元は以下のいずれかの対応を取る義務が生じます。
- 直ちに削除する(請求に応じる)。
- 投稿者に意見を聞き、異議があればその旨を通知する。
- 必要書類の準備: 請求を行う際は、以下の情報を記載した「送信防止措置請求書」を提出する必要があります。
- 侵害された権利の特定: 投稿内容が「プライバシー権侵害」または「名誉毀損」のどちらに該当するか。
- 侵害されたとする理由: 投稿内容の具体的内容と、なぜそれが違法な特定情報であるのかの法的・事実的な説明。
- 特定電気通信による情報の流通によって権利が侵害されたことの疎明資料: 上記で保全した証拠(スクリーンショットなど)。
- 手続きの流れ:
- 請求書をコンテンツプロバイダに送付(内容証明郵便など、送付記録が残る方法が望ましい)。
- プロバイダが投稿者に意見照会(約1~2週間)。
- 投稿者から「削除に同意する」旨の返答があれば、削除が実行されます。
- 投稿者から「削除に異議がある」旨の返答があった場合、プロバイダは削除を行いません。この場合は、次に述べる裁判所への削除仮処分を検討する必要があります。
裁判所を通じた削除仮処分の活用(法的措置)
特定行為による被害が甚大で緊急性が高い場合や、サイト運営元が自主的な削除にも送信防止措置請求にも応じない場合、裁判所の力を借りて強制的に削除を実現します。
1. 削除仮処分の申立てとその緊急性
削除仮処分とは、裁判所に対して、情報の違法性が高いことを疎明し、「仮に」その情報の削除を命じてもらう手続きです。これは「訴訟(本裁判)」とは異なり、非常に迅速な手続きであり、特定情報の緊急削除には最も有効な手段の一つです。
- 迅速性の確保: 通常の訴訟が年単位の時間がかかるのに対し、仮処分は最短で数週間程度で結論が出る可能性があります。特定情報の拡散防止という緊急の目的に非常に適しています。
- 裁判所の強制力: 裁判所が削除を命じた場合、サイト運営元はこの命令に従う義務があります。命令が出たにもかかわらず削除しない場合、間接強制金(命令に従わない日数に応じて罰則的に金銭を支払わせる仕組み)の適用を受けることになります。
2. 申立ての手続きと必要書類
削除仮処分の申立ては、被害者側が裁判所に以下の内容を提出して行います。
- 申立書: 削除を求める投稿のURL、侵害された権利(プライバシー権または名誉権)、違法である具体的な理由などを記載。
- 疎明資料(証拠): 上記で保全したスクリーンショットや動画、被害の実態を示す資料など。
- 担保金(保証金)の準備: 申立が認められた場合、裁判所は、万が一削除が不当であった場合に備えて、被害者側に担保金(保証金)を供託するよう命じます。金額は数十万円程度が目安ですが、事案によって異なります。この担保金は、最終的に削除が正当であったと判断されれば全額返還されます。
3. 削除仮処分命令から執行までの流れ
- 申立てと審尋: 申立書を裁判所に提出。裁判官が双方の主張を聞くための審尋(非公開の話し合い)が行われることがあります。
- 担保金の供託: 裁判所が「削除すべき」と判断した場合、被害者は指定された担保金を裁判所に供託します。
- 削除仮処分命令の発令: 供託後、裁判所からサイト運営元に対し、特定情報の削除を命じる仮処分命令が発令されます。
- 強制執行: この命令をサイト運営元に送達することで、事実上の削除が強制されます。
特定行為による情報は、放置すればするほど被害が雪だるま式に拡大します。自力での対応が難しいと感じた場合や、相手が法的措置を前提とした対応を求めてきた場合は、すぐにネット削除に関する実績を持つ専門家に相談し、上記のいずれかの手段を迅速に実行に移すことが、被害を食い止め、平穏を取り戻すための鍵となります。
加害者向け:特定行為をしてしまった際の法的リスクと自主的な削除の重要性

特定行為は、しばしば「軽い気持ちで」「正義感から」行われてしまうことがありますが、その結果は極めて重大な法的責任を伴います。加害者側は、安易な情報公開が自身と家族の人生を脅かすリスクがあることを深く認識する必要があります。
既に特定行為を行ってしまった、あるいは他人の特定情報拡散に加担してしまったと認識している場合、被害を最小限に抑えるためには、迅速かつ適切な対応が不可欠です。
自主的な削除の推奨とその後の法的影響
特定情報が公開された後、被害者からの削除請求や法的措置が行われる前に、加害者自身が自主的に投稿を削除することは、自身の法的責任を軽減するための最も重要な初動対応となります。
1. 被害の拡大防止と刑事処分の軽減
特定行為による名誉毀損罪や侮辱罪は、被害者の告訴(親告罪)があって初めて警察が捜査に着手するものが多くあります。
- 被害の回復・抑止: 投稿を自主的に削除することは、情報の拡散を食い止め、被害者の精神的苦痛や社会的信用低下を阻止する最大の措置となります。この「被害の回復努力」は、後の民事訴訟における損害賠償額の減額要素として、また、刑事告訴された場合の不起訴処分や刑罰の軽減(情状酌量)の重要な材料として考慮されます。
- 「違法性の認識」の示唆: 投稿を放置し続けることは、「特定情報が違法なものであると認識しながらも意図的に公開し続けた」と判断され、悪質性が高いと見なされる可能性があります。これに対し、迅速な自主削除は、少なくとも「行為の違法性を認識し、反省している」という姿勢を示すことにつながります。
2. 自主的な削除だけでは解決しない法的責任
注意すべき点として、自主的に投稿を削除したからといって、過去の法的責任が完全に消滅するわけではないという事実です。
- 削除前の損害賠償責任: 投稿が公開されていた期間に発生した被害(精神的苦痛、名誉の毀損など)に対する民事上の損害賠償責任は依然として残ります。被害者は、削除後の情報であっても、証拠(スクリーンショットなど)を保全していれば、加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。
- 告訴の取り下げ交渉: 警察に被害届が提出され、捜査が開始されたり、被害者が告訴に踏み切ったりしている場合、自主削除だけでは刑事手続きは止まりません。この場合、被害者と真摯に向き合い、示談交渉を通じて損害を賠償し、告訴を取り下げてもらうことが、刑事罰を回避するための唯一の道となります。
和解・示談交渉による早期解決の可能性と注意点
加害者として最も現実的かつ迅速に事態を収束させる方法は、被害者との間で和解または示談を成立させることです。これは、裁判所を通じた法的措置よりも、時間的・経済的なコストを抑えられる可能性があります。
1. 示談交渉の開始と内容
示談交渉は、通常、被害者側から内容証明郵便や訴状などで通知が来た時点、あるいは加害者側から接触を試みる形で始まります。
- 謝罪の表明と損害賠償の提案: まず、特定行為を行ったことに対する心からの謝罪を明確に伝えます。その上で、被害者に対して生じさせた精神的苦痛や経済的損害に見合う損害賠償金(慰謝料)の支払いを提案します。慰謝料の額は、特定された情報の種類、拡散の程度、被害者の職業や社会的地位などによって大きく変動します。
- 再発防止の約束: 示談の条件として、今後一切、被害者本人や関係者に対して接触したり、情報を拡散したりしない旨を明確に約束します。
- 守秘義務条項: 示談成立後、双方が示談の内容について口外しない守秘義務を定めることも一般的です。
2. 示談交渉における専門家の役割
加害者自身が直接被害者と交渉しようとすると、感情的な対立が生じやすく、交渉が難航するケースが多くあります。
- 交渉の窓口として: ネットトラブルや誹謗中傷事案の示談交渉に精通した専門家を介することで、冷静かつ客観的な立場で交渉を進めることができます。専門家は、法的な相場感に基づいた適正な賠償額を提示し、加害者の反省の意思を被害者に正確に伝える役割を果たします。
- 示談書の作成: 和解が成立した場合、その内容を明確に記した示談書を作成することが必須です。示談書には、賠償額、支払い方法、再発防止の誓約、そして「本件に関して今後一切、民事上・刑事上の請求を行わない(清算条項)」という条項を盛り込むことが重要です。特に刑事告訴の取り下げを条件とする場合は、その旨を明確に記載することで、後の法的リスクを大幅に低減できます。
特定行為の予防と企業の危機管理体制

特定行為のターゲットとなるのは、個人だけでなく、その個人が所属する企業や組織も含まれます。
従業員や役員が特定された場合、企業情報が流出し、企業イメージの棄損や風評被害に直結するからです。特定行為は、個人の問題にとどまらず、組織全体の危機管理として対応すべきテーマです。
ネットモニタリングによる特定リスクの早期発見
特定行為は、情報が公開された直後の初期段階で発見し、対応することが極めて重要です。時間が経過すればするほど、情報の拡散範囲が広がり、削除が困難になります。
1. 検索エンジンとSNSの定期的なチェック
企業は、特定の従業員や役員の名前、あるいは自社名と関連性の高いキーワードについて、定期的なネットモニタリングを実施することが必須です。
- 自社名・製品名: 企業名、主要製品・サービス名、ブランド名、商標など。
- 役員・主要従業員名: 代表取締役や部門責任者、広報担当者など、公的な発言機会が多い人物の実名や、過去に使用していたニックネームなど。
- 関連キーワード: 「(企業名)+不祥事」「(役員名)+特定」「(製品名)+炎上」など、ネガティブなキーワードとの組み合わせで検索を行います。
2. サジェスト機能・関連検索ワードのチェック
検索エンジン(Google, Yahoo!など)の検索窓に入力した際に自動表示されるサジェスト機能や、検索結果の下部に表示される関連検索ワードは、世間の関心度を反映しており、特定情報が広がり始めている初期の兆候を示すことがあります。
- サジェスト汚染の確認: 企業名や役員名に続けて「逮捕」「住所」「特定」といったネガティブなワードが表示され始めた場合、これは既に特定行為が発生し、多くの人がその情報に関心を持っていることを示します。
- 予防的な削除対策: サジェスト汚染が発生した場合、まだ情報が拡散していなくても、直ちに検索エンジンの運営元に対し、サジェストワードの削除(非表示化)申請を行うことが、風評被害を未然に防ぐための重要な措置となります。サジェストの削除は、その情報が違法性や社会的な不当性を持つことを明確に示す必要があります。
従業員・役員に対するプライバシー教育とSNSガイドラインの徹底
特定行為の最大のきっかけは、従業員や役員自身の不用意な情報発信です。企業内での啓発活動は、特定リスクを根元から断つ予防策となります。
1. プライバシー意識向上のための社内研修
全従業員に対し、自身のSNS利用が企業にもたらすリスクについて理解を深めるための定期的な研修を実施します。
- 「特定されるメカニズム」の理解: 投稿した写真の背景、位置情報(ジオタグ)、日常の行動パターン、他者との関係性など、一見無関係な情報がどのように組み合わされて個人特定に至るのか、具体的な事例を交えて解説します。
- 私的利用と公的立場の線引き: プライベートなSNS利用であっても、企業名や役職名が知られている以上、その発言は「企業の一員としての発言」と見なされるリスクがあることを徹底させます。
2. 厳格なSNS利用ガイドラインの策定と順守
企業は、従業員のSNS利用に関する具体的なルールを定めたガイドラインを策定し、その順守を義務付けます。
- 機密情報の非公開: 業務上の機密情報や、顧客情報、社内の人間関係に関する情報の公開を厳しく禁止します。
- 位置情報(ジオタグ)のオフ: 投稿する写真や動画から、位置情報が自動で付加されないよう設定をオフにするよう徹底させます。
- 匿名アカウントの管理: 匿名アカウントであっても、そこでの特定行為や誹謗中傷は、企業の名誉を毀損する可能性があることを明確にし、発覚した際の厳格な処分規定を設けます。
- 特定被害時の報告義務: 万が一、自身や同僚が特定行為の被害に遭った場合、直ちに上長や広報部門、危機管理チームに報告する義務を課します。これにより、企業が一元的に情報を把握し、迅速な削除対応に着手できるようになります。
特定行為の予防は、デジタル時代の企業経営において、リスクマネジメントの最重要課題の一つです。個人の意識改革と組織的な監視体制の両輪で、特定リスクに備える必要があります。
まとめ:ネットの自由と責任ある利用
本記事では、深刻化するネット上の「特定行為」について、その法的定義、被害の実態、そして被害者・加害者双方の立場からの具体的な対処法を詳細に解説しました。
特定行為は、現代のインターネット社会における自由と匿名性の光と影を象徴する問題です。ネットの匿名性は、確かに自由な言論を保障する側面を持ちますが、それが他者のプライバシー権や名誉権を不当に侵害する行為に利用されるとき、その匿名性は法的責任から免れる盾とはなりません。
特定情報が一度ネットに公開されると、その拡散を完全に止めることは極めて困難であり、被害者の人生に長期にわたる影を落とします。だからこそ、被害に遭われた方は迅速な証拠保全と法的手段(送信防止措置請求、削除仮処分)を通じて、情報の削除を強力に進める必要があります。一方、特定行為に加担してしまった方は、自主的な削除と被害者への真摯な謝罪、示談交渉を通じて、自身の法的リスクを最小限に抑える責任があります。

一般社団法人ネット削除協会は、ネット上の誹謗中傷や特定行為による被害から個人と企業の権利を守るため、具体的な削除ノウハウと法的な知識を提供し続けています。
ネットの自由な利用を守るためには、一人ひとりがその発言に責任を持ち、他者の人権を尊重することが不可欠です。もしあなたが特定行為の被害に遭われた場合、あるいは特定行為のリスクに不安を感じている場合は、決して一人で悩まず、専門機関に相談してください。デジタル時代の安全と安心は、適切な知識と迅速な行動によってのみ守られます。
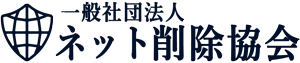
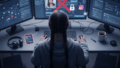

コメント