
近年、私たちの生活に深く浸透したマッチングアプリやオンラインゲームは、新しい出会いや趣味を共有する場として欠かせないものとなりました。しかし、その利便性の裏側で、「ネット晒し」という深刻なプライバシー侵害、名誉毀損のリスクが急増しています。
「晒し」とは、アプリやゲーム内でのトラブルをきっかけに、相手の個人情報やプライベートなやり取りのスクリーンショット、さらには誹謗中傷と結びつけたプロフィール画像などを、SNSや匿名掲示板、暴露系アカウントで不特定多数に公開する行為です。これにより、被害者は精神的な苦痛を受けるだけでなく、実生活での人間関係や仕事、就職活動にまで悪影響が及ぶ「デジタルタトゥー」を刻まれてしまう可能性があります。
特に問題となるのは、匿名性の高い環境での「晒し」が、瞬く間に拡散されてしまうことです。例えば、マッチングアプリのプロフィールに記載していた職場や居住地が公開されたり、ゲーム内での発言の一部だけを切り取られ、悪意をもって解釈された情報が拡散されたりするケースが目立ちます。一度ネット上に流出した情報を完全に消し去ることは極めて困難であり、被害が拡大する前にいかに迅速かつ適切に対処できるかが、その後の人生を左右すると言っても過言ではありません。
一般社団法人ネット削除協会には、「やり取りを晒されたがどうすればいいか」「相手の顔写真も拡散されているが削除できるのか」といった、切迫した相談が日々寄せられています。この問題は、単なるネット上のいざこざでは済まされません。名誉毀損、プライバシー侵害、場合によっては脅迫や業務妨害など、法的な問題に発展する深刻なトラブルです。

この記事では、マッチングアプリやオンラインゲームにおける「晒し」被害に遭った、あるいは遭いそうだと感じている方々に向けて、流出してしまった個人情報や誹謗中傷投稿を削除するための具体的なノウハウを解説します。
プラットフォームへの通報から、法的な手続きを用いた削除請求、そして二度と同じ被害に遭わないための予防策まで、被害を最小限に食い止め、再び安心してネットを利用できるようになるためのロードマップを詳しくご紹介します。ご自身の信用とプライバシーを守るために、ぜひ最後までお読みください。
ネット晒し行為の法的な問題点と削除の根拠

ネット上での「晒し」行為は、被害者の権利を侵害する違法行為です。削除を成功させるためには、その行為が法的にどのような問題を持つのかを正確に理解し、それを根拠にプラットフォームや裁判所に訴える必要があります。
晒し行為が該当する主な権利侵害
晒し行為は、主に以下の3つの権利を侵害します。これらを削除請求の根拠とします。
名誉毀損罪・名誉毀損(民事)
「晒し」られた情報が、被害者の社会的評価を低下させる内容である場合、名誉毀損に該当します。例えば、「〇〇は詐欺師だ」「この人は不倫している」など、具体的な事実を摘示して信用を傷つけるケースです。 たとえその内容が真実であっても、公共性・公益性がない場合は名誉毀損が成立する可能性があります。虚偽の情報であれば、違法性はより高まります。
プライバシー権の侵害
マッチングアプリやゲーム内での非公開の会話のスクリーンショット、個人的な写真、メールアドレス、電話番号、具体的な居住地や職場などの「私生活上の事実」を、無断で公に晒す行為は、プライバシー権侵害に該当します。 「誰もが知られたくない」と感じる情報を公開された場合、この権利侵害を主張できます。
肖像権・パブリシティ権の侵害
アプリのプロフィール画像やゲームのアバター画像など、顔や容姿が特定できる画像を無断で公開された場合、肖像権侵害に該当します。 特に著名なインフルエンサーやゲーム実況者などの場合、その経済的価値を侵害するとしてパブリシティ権侵害も問題になります。
削除請求の法的根拠
ネット上の違法な投稿の削除請求は、主にプロバイダ責任制限法第3条に基づいて行われます。 この法律は、権利を侵害された者が、情報の送信を防止するために、プロバイダ(サイト管理者やサーバー管理者)に対して削除を求めることを認めています。上記の権利侵害のいずれかが認められる場合、「権利が侵害されたことが明白である」として削除請求が可能となります。
ネット晒し被害発生時の超初期対応と証拠保全

晒し被害に気づいた直後の対応が、その後の削除成功率と被害の拡大防止に最も重要です。感情的にならず、冷静に以下の手順を踏んでください。
拡散状況の確認と記録
「晒し」の投稿を見つけたら、まずは以下の情報を正確に記録(証拠保全)してください。
投稿のURL・日時・内容を正確に記録する
問題の投稿がされた正確なURL(ウェブアドレス)を控えてください。これは削除請求において、特定の投稿を識別するために必須の情報です。 また、投稿が確認できた日時、投稿されたプラットフォーム名(X、Instagram、5ちゃんねるなど)を記録します。 さらに、投稿の全文をコピー&ペーストして文書ファイルに保存してください。
スクリーンショットやウェブ魚拓による保全
投稿画面全体をスクリーンショットで撮影してください。その際、以下の情報が映るようにすることが重要です。
- 投稿の内容全体
- 投稿日時
- 投稿者のアカウント名
- 画面上部のURLバー ウェブ魚拓サービス(魚拓、ウェブアーカイブなど)を利用し、投稿を保全することも有効ですが、デジタル証拠として提出する場合、スクリーンショットのほうがより確実性が高い場合があります。
投稿者への直接連絡の是非と注意点
晒しを行ったアカウントが特定できる場合でも、被害者本人が直接連絡を取ることは推奨されません。
直接交渉が危険な理由
直接連絡を取ることで、かえって相手を刺激し、さらなる誹謗中傷や情報の拡散を招くリスクが高まります。また、相手が加害行為を認めず、証拠隠滅を図る可能性もあります。 連絡が必要な場合は、必ず専門家に依頼し、冷静かつ法的な視点から対応することが安全です。
削除依頼が可能な場合はまず依頼する
ただし、相手が友人・知人など特定可能な人物で、かつトラブルが軽微で、冷静な話し合いによって解決が見込める場合に限り、「弁護士に相談済みであること」を冷静に伝えつつ、削除を依頼することも選択肢の一つです。その際も、必ず事前に全ての証拠を保全してからにしてください。
プラットフォーム別:晒し投稿を削除するための通報ノウハウ

自力での削除対応の第一歩は、投稿先のプラットフォーム運営会社に「利用規約違反」または「権利侵害」を理由に通報・報告することです。各プラットフォームには、専用の報告窓口や手順があります。
X(旧Twitter)での「晒し」削除
Xでは、プライバシー侵害やハラスメント行為に対するポリシーが厳格に定められています。
プライバシー侵害(個人情報)の報告
具体的な手順:
- 問題のツイートにある「…」(メニューアイコン)をタップし、「ツイートを報告」を選択します。
- 「このアカウントについて」→「このアカウントに問題がある」→「特定の人物になりすましている、または特定の人について言及している」を選択します。
- 「非公開の個人情報を含む」を選択し、晒された情報が「電話番号、住所、免許証などの情報」、または「非公開の性的画像・動画」のいずれに該当するかを選択します。
- 報告フォームに、晒された情報が非公開であること、そして被害者本人であることを証明する情報を入力します。身分証明書などの提出を求められる場合があります。
ハラスメント・誹謗中傷の報告
具体的な手順:
- 「このアカウントについて」→「私または私が知っている誰かに対するハラスメント」を選択します。
- ハラスメントの種類として、「中傷、嫌がらせ、脅迫」などを選択し、投稿が「ターゲットを絞ったハラスメント」に該当することを主張します。
- 報告内容に、投稿によって社会的評価が低下していることや、精神的な苦痛を受けていることを具体的に記述します。
Instagram・Facebookでの「晒し」削除
Meta社が運営するInstagramやFacebookは、コミュニティ規定に厳しく、特に「いじめや嫌がらせ」「個人情報の公開」に関するポリシーが明確です。
コミュニティ規定違反に基づく報告
具体的な手順:
- 問題の投稿(フィード、ストーリーズなど)またはアカウントの「…」をタップし、「報告」を選択します。
- 「不適切である」→「嫌がらせやいじめ」または「プライバシー侵害」を選択します。
- 「個人情報の共有」を明確に選び、無断で共有された情報が被害者本人に関するものであることを証明する情報(本人のアカウント情報など)を提供します。
- 特に、脅迫的なメッセージや繰り返し行われる誹謗中傷は「いじめ」として報告します。
匿名掲示板(5ちゃんねる等)での削除
匿名掲示板は削除が最も難しいプラットフォームの一つですが、適切な手続きを踏めば削除は可能です。
削除依頼フォームの利用
多くの匿名掲示板には、「削除依頼フォーム」が設置されています。 具体的な手順:
- 掲示板の削除ガイドラインを確認し、名誉毀損、プライバシー侵害、わいせつ物陳列のいずれに該当するかを特定します。
- フォームに、スレッド名、レス番号、削除理由(法的な根拠)を具体的に記述します。
- この際、「感情的ないやがらせ」といった抽象的な表現ではなく、「〇〇は虚偽の事実の摘示であり、名誉毀損に該当する(民法709条)」といった法的な言葉を用いることが、削除の可否を判断する管理者に対して有効です。
裁判所を介した削除仮処分命令の申し立て

プラットフォームへの通報で削除が実現しない場合や、迅速な削除が必要な場合は、裁判所を介した「削除仮処分命令」の申し立てが最も確実な手段となります。
削除仮処分とは
仮処分とは、正式な訴訟(裁判)を待たずに、緊急で暫定的な措置を裁判所に求める手続きです。ネット上の違法な情報拡散は、時間が経つほど被害が拡大するため、「緊急性」が高いと認められやすく、この手続きが広く利用されています。
申し立ての具体的なステップ
1. 証拠の整理と法的主張の準備
まず、前述の方法で保全した証拠(スクリーンショット、魚拓、URLリストなど)を整理します。 次に、投稿内容が「名誉毀損」または「プライバシー侵害」のいずれに該当するかを特定し、その違法性を主張する申立書を作成します。 申立書には、以下の点を具体的に記述する必要があります。
- 投稿内容とURL
- 投稿が虚偽またはプライバシー情報であること
- 投稿によって被害者が受けた具体的な被害(精神的苦痛、業務への影響など)
- なぜその投稿を直ちに削除する必要があるのか(緊急性の主張)
2. 担保金の供託
裁判所は、仮処分命令を出す際、申立人(被害者)に対して、万が一削除命令が不当であった場合に、相手方(投稿者やプロバイダ)が被る損害を補填するための「担保金」の供託を命じることが一般的です。 担保金の額は事案によりますが、数十万円から数百万円程度となるケースが多いです。この担保金は、最終的に権利侵害が認められれば返還されます。
3. 審尋(しんじん)と命令の発令
申立書が提出されると、裁判所は当事者双方(被害者側とプロバイダ側)から事情を聞く「審尋」という手続きを行います。 審尋を経て、裁判所が投稿の違法性や緊急性を認めれば、プロバイダ(サイト管理者)に対して投稿を削除するよう命じる「削除仮処分命令」が発令されます。 この命令が出た場合、プロバイダは原則として直ちに削除に応じる義務を負います。
加害者の特定(発信者情報開示請求)と損害賠償

投稿の削除は最も重要な目的ですが、被害の回復と再発防止のためには、晒しを行った加害者(発信者)を特定し、責任を追及することも重要です。
発信者情報開示請求の仕組み
晒しを行った投稿者は通常、匿名(またはハンドルネーム)です。その正体を明らかにするために、プロバイダ責任制限法第5条に基づき、「発信者情報開示請求」を行います。
2段階の請求手続き
請求は通常、以下の2段階で行われます。
- コンテンツプロバイダ(サイト管理者)へのIPアドレス開示請求: まず、Xや匿名掲示板などのサイト管理者に対し、投稿時に利用されたIPアドレス(ネット上の住所にあたるもの)の開示を請求します。 この請求も、裁判所への仮処分命令の申し立てによって行われることが一般的です。
- アクセスプロバイダ(通信事業者)への氏名・住所開示請求: 開示されたIPアドレスに基づき、そのIPアドレスを割り当てたアクセスプロバイダ(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなどの通信事業者)を特定します。 次に、アクセスプロバイダに対し、投稿時のIPアドレスに対応する契約者情報(氏名、住所など)の開示を請求します。この請求は、通常、正式な訴訟(発信者情報開示請求訴訟)によって行われます。
損害賠償請求と刑事告訴
加害者の氏名・住所が特定できた場合、以下の法的手段を検討します。
損害賠償請求
名誉毀損やプライバシー侵害による精神的苦痛(慰謝料)や、削除にかかった弁護士費用などについて、民事訴訟を起こして損害賠償を請求します。 被害の程度や拡散状況、加害行為の悪質性によって賠償額は異なりますが、これにより被害の回復を図ります。
刑事告訴
晒し行為が、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)に該当する場合、警察に被害届を提出し、刑事告訴することも可能です。 これにより、加害者は警察による捜査を受け、起訴されれば罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性があります。特に悪質なケースや、脅迫などが含まれる場合は有効な手段です。
二次被害・拡散を防ぐための安全対策と予防策

晒し被害のダメージを最小限に抑えるためには、流出した情報の削除と同時に、今後の二次被害や新たなトラブルを防ぐための安全対策を講じることが極めて重要です。
アカウント設定の徹底的な見直し
プライバシー設定の強化
マッチングアプリやSNSのプライバシー設定を必ず見直し、以下の点を徹底してください。
- 非公開アカウント(鍵垢)の活用: SNSは、基本的には知人以外に公開しない設定にします。
- タグ付け・メンションの制限: 自分を勝手にタグ付けしたり、メンションしたりできる人を制限します。
- 位置情報(GPS)のオフ: 投稿に位置情報が付加されないよう設定をオフにします。
- 検索エンジンのインデックス除外: 自分のアカウントがGoogleなどの検索エンジンに表示されないよう、設定を変更します。
使用画像の厳選と管理
マッチングアプリなどで使用する写真は、安易に以下のものを使用しないでください。
- 背景に自宅や職場が特定できるものが写り込んでいる写真。
- 過去に別のSNSで広く公開した写真。
- 顔の半分を隠すなど、敢えて「検索されにくい」写真を選ぶことも自己防衛策の一つです。
デジタルタトゥーの監視と検索結果からの削除
自身の名前の定期的な検索
ご自身の氏名やハンドルネーム、勤務先など、個人と結びつくキーワードを定期的に「エゴサーチ(自己検索)」し、新たな「晒し」の痕跡がないか監視してください。 特に、GoogleやBingの検索結果に、すでに削除したはずの投稿の「キャッシュ(過去の記録)」や「魚拓サイト」が表示されていないかを確認します。
検索結果からの削除請求
すでに投稿が削除されたにもかかわらず、Googleなどの検索結果にスニペット(抜粋)として表示され続けている場合は、検索エンジンに対して「削除されたコンテンツの削除リクエスト」を行う必要があります。 具体的な手順:
- Google Search Console内の「古くなったコンテンツを削除」ツールを利用します。
- 表示されている古いURLを入力し、「削除リクエスト」を送信します。
- この際、元のウェブサイトではすでに情報が削除されていることが必須条件となります。
トラブル発生時の冷静なコミュニケーション
マッチングアプリやオンラインゲーム内で相手との意見の食い違いが生じたり、関係が悪化したりした場合は、感情的な言葉遣いを避け、冷静に対処してください。 やり取りのスクリーンショットは、後々「晒し」の証拠として利用されるリスクがあります。危険を感じたら、直ちに関係を断ち、ブロックするなどの対応を取り、やり取りを最小限に留めることが大切です。
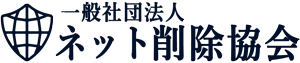

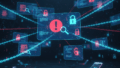
コメント